公開日:2024.1.15(更新日:2025.3.14)
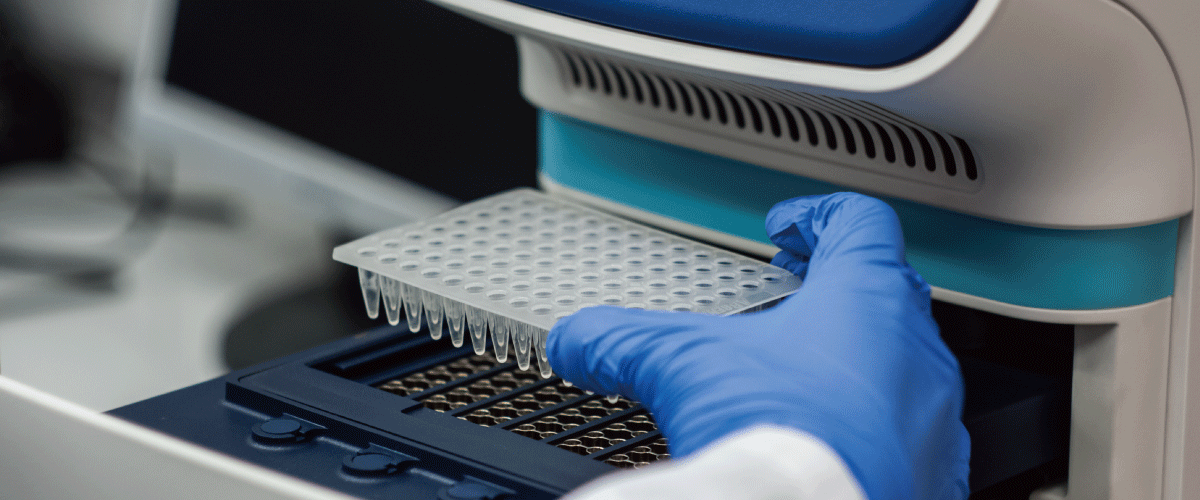
この記事では、リアルタイムPCRの原理や、手法の違い、装置の選び方などについて解説いたします。ぜひ最適な手法や、装置の選定にお役立てください。
実験内容に合わせた装置選びに迷われた際は、池田理化がご要望にあわせた最適な装置をご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
リアルタイムPCRについて相談してみる
目次
リアルタイムPCRとは

リアルタイムPCRは、PCRによるDNA増幅をリアルタイムにモニタリングすることで、テンプレートDNA(※1)の定量を行う「定量PCR」の一つです。
PCR後に電気泳動で増幅産物の確認を行う必要がないため、操作が簡便で迅速に結果が得られることや、コンタミネーションのリスクが低いことなどが特長です。
このため、遺伝子発現解析のほか、疾患の診断や治療法の選択に使われるSNPsタイピング、ウイルスや病原菌の検出など、多種多様な用途で用いられています。
※1… 最初の鋳型となるDNAのこと
PCRやデジタルPCRとの違い

リアルタイムPCRは、「PCR」や「デジタルPCR」とは何が違うのでしょうか?それぞれについて簡単にご説明いたします。
PCRとは
PCRは「ポリメラーゼ連鎖反応(polymerase chain reaction)」の略称ですが、PCRを行う装置の通称としてもよく用いられます。装置名としては「サーマルサイクラー」と呼ばれることも多いです。
PCRは3つのステップで構成されます。「熱変性」ステップでは、鋳型となるDNAとDNA合成酵素(DNAポリメラーゼ)、プライマー(※2)と呼ばれるオリゴヌクレオチドなどを混合した反応液を、94~98℃の高温にしてDNAの変性を促し、二本鎖DNAを一本鎖にします(左図-①)。
次に「アニーリング(※3)」ステップでは、反応液を50~65℃まで冷却して、一本鎖DNAにプライマーを結合させます(左図-②)。
さらに「伸長」ステップでは、DNAポリメラーゼが働く68~72℃に上げることで、プライマーの結合部分を起点に二本鎖DNAが合成されます(左図-③)。この熱サイクルを繰り返すことで、DNAは指数関数的に増幅します。
あくまでDNA増幅を行うための装置なので、ターゲット遺伝子の発現有無は電気泳動で確認する必要があります。
※2… 鋳型DNAに相補的な塩基配列を持つ一本鎖DNAのこと。増幅したい領域を挟んで2か所に設計する
※3… 一本鎖DNAが相補的な配列を持つDNAに結合すること
デジタルPCRとは

デジタルPCRはリアルタイムPCRよりもさらに高感度・高精度な定量を可能とする技術です。
0~1分子のDNAが微小区画に分散するようにサンプルを限界希釈した状態でPCRを行い(上図-①)、微小区画ごとの増幅シグナルを検出します。このため、リアルタイムPCRでは検出できないような微量な遺伝子発現量でも検出することが可能です。
また、微小区画内のターゲットとなるDNAが0分子であれば増幅シグナルは得られず、1分子の場合は増幅シグナルを得ることができるので、これをカウントすることでターゲット遺伝子の発現量を絶対的に測定することが可能です(上図-②)。
後述するように、リアルタイムPCRでも「絶対定量法」と呼ばれる手法がありますが、これはスタンダードとなるサンプルとの比較によって定量を行う方法です。したがって、デジタルPCRの方がより高精度な定量が可能と言えます。
PCR、リアルタイムPCR、デジタルPCRの比較
PCR、リアルタイムPCR、デジタルPCRの特徴を以下にまとめました。
|
概要 |
定量性 |
感度 |
精度
|
操作性
|
費用
|
おすすめの用途
|
| PCR |
熱サイクルを反復してPCRを促し、DNAを増幅する |
△ |
△ |
△ |
△ |
◎
安価 |
シーケンシング、ジェノタイピング、クローニングなどを目的としたDNA増幅
|
| リアルタイムPCR |
PCRによってDNAを増幅し、その増幅率をリアルタイムでモニタリングすることで、DNAの定量を行う |
〇
|
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
・遺伝子発現の定量
・マイクロアレイ検証
・品質管理およびアッセイの検証 など |
| デジタルPCR |
限界希釈したサンプルDNAを微小区画内に分散させてPCRを行い、DNAが増幅した微小区画の数を数えて定量を行う
|
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
△
高価 |
・ウイルス量の絶対定量
・核酸標準品の絶対定量 など |
池田理化では実施される実験内容に応じて、最適な機器をご提案させていただきます。
どの装置がご自身の使用環境に最適かお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
装置の選び方について相談してみる
リアルタイムPCRの原理と主な手法
リアルタイムPCRでは、PCR産物が指数関数的に増幅する様子をリアルタイムにモニタリングすることで、絶対的、あるいは、相対的にテンプレートDNA量を定量することができます。この増幅の様子を図に表したものが増幅曲線です(左図)。増幅曲線は、PCR産物が蛍光検出できる量に達すると立ち上がり始め、指数関数的に上昇した後、シグナルが横ばいとなるプラトーに達します。
また、PCR産物量がある一定量に達したところを閾値(Threshold)として設定し、閾値と増幅曲線が交わる点を各サンプルのCt値(Threshold Cycle)と呼びます。
テンプレートDNA量が多いほどPCR産物は早く増えるため、Ct値は小さくなり(左図-点A)、少ないほどCt値は大きくなります(左図-点B)。このようにテンプレートDNA量とCt値は相関関係にあり、Ct値はリアルタイムPCRによる定量化において重要な値です。
蛍光検出方法の種類
リアルタイムPCRでは、PCR産物の増幅量のモニタリングに蛍光物質を用います。
蛍光物質による検出方法には、大きく分けて「インターカレーター法」と「蛍光標識プローブ法」があります。
蛍光標識プローブ法は、使用するプローブによって多くの種類に分けられますが、ここでは2種類の手法を紹介します。
インターカレーター法

インターカレーターは、単体では蛍光を発しませんが(上図-②)、二本鎖DNAに結合した状態で励起光を照射すると蛍光を発します(上図-③)。
この性質を利用し、反応に伴う蛍光強度を測定することで、PCR産物の生成量をモニタリングする方法を「インターカレーター法」と呼びます。
おすすめの用途
メリット
- ターゲットDNAに応じた蛍光プローブが必要ない
- 低コストで反応系の構築が比較的容易
デメリット
- 配列非特異的に蛍光物質が二本鎖DNAに結合するため、プライマーダイマー(※4)などの非特異的増幅産物も検出されてしまうことがある
比較的手軽に始められるのがこの手法のメリットですが、上述のようなデメリットがあるため、反応自体に特異性が求められます。
したがって、プライマーの設計や反応条件が最適化できている場合におすすめです。
※4… プライマー同士で相補的な配列のある場合にその部分がアニーリングし、ターゲットである鋳型DNA同様に増幅してしまった目的外の増幅産物。サイズが短いため、鋳型DNAの増幅産物よりも増幅効率が高いこともあり、検出感度の低下に影響する。
蛍光標識プローブ法
蛍光標識プローブは、片方の末端が蛍光物質、もう片方の末端が蛍光の発生を抑制するクエンチャー物質で修飾されています。蛍光物質は、クエンチャー物質との物理的距離が近いと蛍光を発しませんが、クエンチャー物質との物理的距離が離れると、励起光の照射によって蛍光を発する性質を持っています。
また、プローブはアニーリングのステップでターゲットDNAの任意の配列に特異的にハイブリダイズする(※5)設計になっています。この性質を利用し、反応過程でプローブが分解されることにより発生する蛍光強度を測定することで、PCR産物の生成量をモニタリングする方法を「蛍光標識プローブ法」と呼びます。
※5… DNAやRNAといった核酸が相補的な配列と複合体を形成すること
プローブ法

蛍光標識プローブ法のうち、プローブ法(5'-ヌクレアーゼ法)は、5’末端を蛍光物質、3’末端を蛍光の発生を抑制するクエンチャー物質で修飾したオリゴヌクレオチドをプローブとして用いる方法です(上図-①)。
伸長反応の過程で、Taq DNA ポリメラーゼの持つ5' → 3'エキソヌクレアーゼ活性によってプローブが分解されると、蛍光物質が遊離し、クエンチャーによる抑制がなくなります(上図-③)。
その際に発生する蛍光強度を測定することで、PCR産物の生成量をモニタリングします。
おすすめの用途
メリット
- 増幅したいDNA配列に対して相補的な配列を持つプローブを用いるので特異性が高い
- 最適なプローブが既製品にある場合は、サンプルさえあれば実験が開始できる
デメリット
- コストがかかる
- 最適なプローブが既製品になければ、新たにプローブの設計が必要
上述の理由から、インターカレーター法よりも精度の高い解析結果が必要な場合は、プローブ法がおすすめです。
また、ご自身の求めるプローブが既製品にある場合は、反応条件が最適化されているので、サンプルさえあれば実験を開始することができることもメリットのひとつです。
一方、新たにプローブを設計する場合、プローブがターゲット遺伝子の任意の配列のみに相補的であることのほか、プライマー配列との相補性がないことや、それぞれが最適な位置関係にあるかどうかなど、多くの点を考慮しなければなりません。
継続的にプローブ設計が必要な場合は専用ソフト、単発の場合は受託を活用するのも良いかもしれません。
サイクリングプローブ法

蛍光標識プローブ法のうち、サイクリングプローブ法は、サイクリングプローブと呼ばれるキメラオリゴヌクレオチドをPCR反応系に加えます。
このキメラオリゴヌクレオチドは、RNAとDNAから成り、RNA部分をはさんで片方の末端が蛍光物質、もう片方の末端がクエンチャー物質で修飾されています(上図-①)。
RNase HによってRNA部分が切断されると、蛍光物質とクエンチャー物質の物理的距離が離れ、蛍光を発します(上図-②~③)。この蛍光強度を測定することで、PCR産物の生成量をモニタリングします。
おすすめの用途
メリット・デメリット
- 基本的にはプローブ法と同じ
- ただし、サイクリングプローブ法の場合、プローブのRNA付近に1塩基でも違いがあればRNaseHによる切断は起きず、蛍光は検出されない
上述の通り、1塩基の違いを検出できるため、SNPsタイピングなどを行いたい場合におすすめです。
プローブ法を用いてSNP解析を行う場合は2種類のプローブを用意する必要があるため、ひとつのプローブでSNP解析ができることはサイクリングプローブ法の大きなメリットのひとつです。
定量方法の種類
リアルタイムPCRを活用した定量方法には、絶対定量法と相対定量法の2種類があります。
絶対定量法

絶対定量法は、ターゲット遺伝子のDNA量が既知のサンプルで作成した検量線を用いて、研究対象となるサンプルのターゲット遺伝子の発現量を定量化する手法です。
既知のサンプルを段階希釈して(上図-①)リアルタイムPCRを行うと、そのDNA量の多いサンプルから順に増幅曲線が等間隔で並ぶグラフが作成できます(上図-②)。
それらから得られる各Ct値で検量線を作成し、未知のサンプルのCt値を検量線に当てはめることで、未知のサンプルのDNA量を求めることができます(上図-③)。
おすすめの用途
ターゲット遺伝子の実際のDNA量が知りたい方におすすめです。ただし、下記3点を考慮する必要があります。
- ターゲット遺伝子のDNA量が既知のスタンダードサンプルを用意すること
- スタンダードと研究対象のサンプルの純度と形状が近いこと
- 正確な検量線を作成できること
2については、これらの影響でPCRの反応効率に差が出てしまい、本来のCt値からずれてしまう可能性があることが理由です。
たとえば、スタンダードサンプルの純度だけが極端に高ければ、それと比べて研究対象のサンプルの反応効率は悪くなる可能性があります。
また、スタンダードサンプルがゲノムDNA、研究対象のサンプルがプラスミドDNAであれば、形状が大きく異なるため、これもCt値に影響してしまう可能性があります。
3については、検量線の精度が解析結果の精度に繋がること、また、正確な検量線を作成できることは精度の高いピペット操作ができていることのひとつの目安とできることが理由です。
段階希釈が上手くできていれば等間隔な増幅曲線が得られますが、そうでない場合は値がばらつきます。
リアルタイムPCRでは僅かなテンプレートDNA量の差がCt値に影響するため、実験全体でピペット操作に高い精度が求められます。ピペット自体のメンテナンスもしっかりと行いましょう。
ピペットメンテナンスについて詳しく知りたい(YouTubeへ)
相対定量法

相対定量法は、研究対象となるサンプルのターゲット遺伝子の発現量を、スタンダードとなるサンプルと比較することで相対的に定量化する手法です。
また、サンプル間のばらつきを考慮するため、ターゲット遺伝子の発現量はハウスキーピング遺伝子(※6)などの内在性コントロールによって補正されます。
たとえば、上図のように内在性コントロール遺伝子とターゲット遺伝子のCt値の差が、スタンダードサンプルAで20、研究対象のサンプルBで10ある場合、BはAと比べてCt値に達するのが10サイクル分早いと言えます。
PCR産物は2倍ずつ増えるので、BはAの2の10乗倍のターゲット遺伝子の発現があるということがわかります。
このように、内在性コントロールで補正したターゲット遺伝子の定量値を、スタンダードと比較することで、研究対象となるサンプルの相対的な定量化を行います。
※6… GAPDHやβ-アクチン等、細胞の維持・増殖に不可欠で、多くの組織に共通して常に一定量発現するとされる遺伝子のこと
おすすめの用途
スタンダードと比べて、研究対象のサンプルにおけるターゲット遺伝子の発現量がどれくらい増減しているか知りたい人におすすめです。ただし、下記2点を考慮する必要があります。
- ターゲット遺伝子の発現量が正常なスタンダードサンプルを用意すること
- ターゲット遺伝子の発現量が適切に補正できていること
2については、実験によってどのような補正が「適切」なのか一概には言えませんが、代表的な3つの手法を簡単に比較してみます。
① ΔΔCt法
ハウスキーピング遺伝子はいずれのサンプルでも同程度に発現しており、かつ、PCRの増幅効率は100%であるという想定で定量値を算出する手法です。
この手法では検量線は用いません。
② Pfaffl法
実際にはPCRの増幅効率は100%ではなく、サンプルや条件によってばらつきがある可能性が高いです。
Pfaffl法では、検量線を用いてこのばらつきを補正するため、ΔΔCt法よりも高精度な相対比を算出することができます。
③ Vandesompele法
内在性コントロールは常に一定量発現している遺伝子である必要があります。
ところが、内在性コントロールとして用いられてきたハウスキーピング遺伝子の発現が、実験条件によっては変動するケースがあることが報告されています。
これを考慮するために、Vandesompele法では複数のハウスキーピング遺伝子を用います。
最適なアプリケーションについて相談してみる
リアルタイムPCRを選ぶ8つのポイント

リアルタイムPCRはさまざまなメーカーから発売されていますが、その特長や性能はそれぞれ異なります。装置を選定する際の8つのポイントは以下の通りです。
1.サンプル数・量
装置によって、同時測定できるサンプル数は異なります。96ウェルの装置が一般的ですが、それよりも多い384ウェル、5184ウェルなどもあるため、解析したいサンプル数にあわせて検討しましょう。ブロックごと交換してサンプル数を変えられる装置もあります。
また、必要となる反応液量が少なければ、1解析あたりの試薬量は少なく済みます。一般的にはウェル数が多くなるほど必要な反応液量も少なくなりますが、同じウェル数でも必要な反応液量が異なる場合もあるため、確認するとよいでしょう。
2.温度制御精度
PCRは温度の上昇下降を繰り返す反応のため、装置の温度制御の正確性が反応の成否に関わる場合があります。
また、サンプルを入れたブロック全体の温度を均一に制御できるかどうかも、正確で再現性のある実験結果を得るために重要です。精度の高い制御機能で温度を常に最適化できれば、非特異的な反応を防ぐことができ、反応効率が上がります。
3.加温・冷却速度
PCR反応は温度を上下させることによって進むため、温度の正確性だけでなく、加温や冷却のスピードも重要です。目的温度まで短時間で到達できる装置であれば、PCRそのものにかかる時間を大きく短縮でき、非特異的な反応も抑えることができます。
4.対応蛍光色素数
装置によって、検出できる蛍光色素の種類は異なります。実験で使用したプローブの蛍光標識が検出できなければ定量ができないため、その装置に搭載されている波長域が、使用するプローブの蛍光標識に対応しているかどうか、確認が必要です。
また、2種類以上のターゲットDNAを同時にPCRで増幅し、同時に検出したい場合は、同一のウェルから異なる蛍光色素を正確に検出できるマルチプレックスに対応した装置を選ぶとよいでしょう。
5.グラジエント機能
グラジエント機能は、一つのブロック内でウェルごとに温度勾配を設定できる機能です。PCR反応の最適な温度条件を検討する際、条件を変えながら何度も実験したり、設定温度を変えたPCR装置を複数台動かしたりすると、手間も時間もかかります。
しかし、グラジエント機能を有する装置であれば、一度の実験で最適な温度条件を評価できるため、とても便利です。
6.対応試薬・容器・シール
PCRに使用する試薬は、リアルタイムPCR装置のメーカーごとに発売されており、蛍光検出方法や実験目的によってさまざまな種類があるため、その中から最適なものを選んで使用するのがベストです。他メーカーの試薬を使う場合は、その試薬に含まれる蛍光物質に装置の波長や解析ソフトが対応しているかを確認する必要があります。
また、反応チューブや反応プレート、プレートに貼るシールは、メーカーから各装置の仕様に合わせたものが発売されているので、それを使用するのがおすすめです。装置と異なるメーカーのものを選ぶ場合は、使用する機種に対応しているかどうかを確認しましょう。
7.運転モード(Fastモードの有無)
リアルタイムPCR装置の中には、反応温度を上げ下げするスピードを変えて、1回の結果が出るまでの待ち時間を短縮できる「運転モード」を備えているものもあります。運転モードは通常2種類で、StandardモードとFastモードがあります。
Standardモードは、一般的なリアルタイムPCRの速度で、1時間半~2時間ほどの待ち時間となります。
一方、Fastモードは30~40分など、通常の1/3ほどの時間で結果が出ます(※メーカーによって異なるため、あくまで参考値です)。
Standardモードの方が処理能力は高く、一度に大量のサンプルを処理できますが、限られた時間内で実験を行いたいという場合は、Fastモードのある装置を選ぶのもおすすめです。
8.操作性
タッチパネルの有無や使いやすさ、付属のPCの有無、解析ソフトの内容や使いやすさ、装置の大きさなど、実験室での装置の操作性が良いかどうかも非常に重要です。
タッチパネル搭載のスタンドアロン式であれば、PCなどを使わずにタッチパネル上で実験の設定や増幅曲線の確認などを行うことができます。また、操作方法が分かりやすいか、使用者の言語に対応しているかも大事なポイントです。
リアルタイムPCRには、装置そのものはもとより、検出方法や試薬などにもいろいろな種類があり、装置選びに迷う方も多いのではないかと思います。結局のところ最も大切なのは自分のやりたいことが実現できる装置かどうかです。
池田理化は、1931年の創業以来、研究者の皆さまをサポートしてきたノウハウや経験に基づき、常時3,000 社を超える取り扱いメーカーの製品から最適な機器をご提案します。
選び方に迷ったときや、特別なアプリケーションが必要な場合など、リアルタイムPCRで分からないことがあれば、ぜひ当社までご相談ください。