公開日:2025.3.5(更新日:2025.6.20)

クリーンベンチは、実験室や研究開発、品質管理などの製造現場において、作業エリア内の清浄度を高く保ち、空気中に浮遊するほこりや微生物などの混入からサンプルを保護するために用いられる装置です。
この記事では、これからクリーンベンチを使用する予定の方のために、原理と仕組み、類似機器との違い、使用上の注意点などを説明します。用途に合わせたクリーンベンチの選び方もご紹介しますので、新規購入や買い替え時の検討にお役立てください。
クリーンベンチについて相談してみる
中古機器のお取り扱いがある場合もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
中古のクリーンベンチを探す
目次
クリーンベンチとは

クリーンベンチは清浄度の高い環境を作り出すための箱型装置で、清浄作業台とも呼ばれています。
作業エリアには高性能フィルターを通した清浄な空気が供給され、ほこりや微生物などを含んだ空気は外から流入しない仕組みになっています。一般的な室内環境でも局所的に高い清浄度を実現することができるため、さまざまな分野で活用されています。
ここではクリーンベンチの使用目的、原理や仕組みを見ていきましょう。
クリーンベンチの使用目的
クリーンベンチの使用目的は「コンタミネーション(※1)の防止」です。
主な使用分野は生物学、生化学、医薬品研究などです。微生物や細胞の培養、遺伝子研究、医薬品の調製などにおける「無菌操作」で用いられています。
そのほかにも、半導体や液晶ディスプレイ、電子部品、精密機器、食品の製造工場など、幅広い分野で使用されています。
いずれもコンタミネーションが大きな問題となり得るため、清浄度の高い作業環境を作り出すことのできるクリーンベンチは必須の設備です。
※1 コンタミネーション(contamination)… コンタミとも呼ばれ、「ある物質に本来あるべきでない別の物質が混入すること」を指す。空気中のほこりや微生物などの浮遊物質によってサンプルが汚染されることに加え、汚染されたサンプルから別のサンプルへその汚染が拡大すること(クロスコンタミネーション、交差汚染)も含む。
クリーンベンチの原理と仕組み
クリーンベンチは、作業台の左右・背面を囲われ、上部には屋根、前面にはサッシのある構造です。
機器内部には気流を発生させるための送風機が搭載されており、作業台の真上にあたる天井部分にはHEPAフィルター(※2)が設置されています。HEPAフィルターは、空気中の微粒子を捕集するための高性能なエアフィルターで、作業エリアにはHEPAフィルターを通して清浄化された空気が供給されます。
クリーンベンチの作業エリアは陽圧に保たれており、ほこりや微生物などを含むエリア外の空気はエリア内に流入しない仕組みです。エリア内の空気はサッシ開口部からそのままエリア外に排出されます。
基本的な構造は上述の通りですが、実際にはさまざまな用途に合わせて、上記以外のタイプもあります。
(詳しくは「クリーンベンチの種類」にて後述)
※2 「HEPAフィルター」とは…
High Efficiency Particulate Air Filterの略。この記事の公開日時点で、JIS Z 8122において「定格風量で0.3μmの微粒子を99.97%以上除去可能な粒子捕集率を持ち、かつ、初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルター」と定義されている。ただし、2022年2月21日よりJIS B 9927にて、粒子除去用高性能フィルターの「MPPS(Most Penetrating Particle Size ; 最も透過しやすい粒子径)」の捕集効率に関して定義変更があったため、旧規格のフィルターが新規格の性能を有するとは限らない。最新情報や詳細については「日本規格協会グループHP」の該当規格を参照。
なお、基本的にはHEPAフィルターが採用されているが、さらに高性能なULPAフィルターが採用されている機種もある。ULPAフィルターについては「1-2.フィルターの種類」にて後述。
安全キャビネットやドラフトチャンバーとの違い

クリーンベンチと混同されやすい装置として、安全キャビネットとドラフトチャンバーがあげられます。箱型の形状や気流を制御する点は共通していますが、使用目的や仕組みは異なるため、注意が必要です。
ここではそれぞれの基本的な構造やクリーンベンチとの違いを説明します。用途や機能の違いを理解し、正しく使い分けましょう。
安全キャビネットとの違い

安全キャビネットの主な使用目的は「バイオハザード防止」「作業者の安全性の確保」です。病原体や遺伝子組換え生物等などを取り扱う際に、作業者や周囲環境の安全性を確保し、バイオハザードを未然に防ぐために用います。
安全キャビネットは、作業エリア内を陰圧に保つことで、病原体や遺伝子組換え生物等などの漏洩を防ぐ仕組みです。エリア内の汚染された空気はHEPAフィルターを通して清浄化されてから排出されます。
一方で、クリーンベンチの作業エリア内は陽圧に保たれており、作業エリア内の空気はそのままエリア外へ排出されます。したがって、バイオハザード対策が必要な病原体や遺伝子組換え生物等などを取り扱う場合は、クリーンベンチではなく、安全キャビネットを使用しなければなりません。クラスⅡ以上の安全キャビネットであれば「無菌操作」も可能です。
安全キャビネットについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
安全キャビネットとは?種類や機能と選定のポイントをご紹介
ドラフトチャンバーとの違い
ドラフトチャンバーの使用目的は「有機溶剤や特定化学物質からの作業者の保護」「外気汚染の防止」です。
ダクトを通して作業エリア内の空気をすべて外部に排出する構造で(※3)、作業者が有機溶剤や特定化学物質などの有害物質を安全に取り扱うために使用されます。また、外気汚染を防ぐため、排出される空気中の有害物質はスクラバーや活性炭フィルターによって除去されます。
HEPAフィルターを通して清浄な空気が作業エリア内に供給されるクリーンベンチとは異なり、ドラフトチャンバーはサッシ開口部から作業エリア内へエリア外の空気が直接取り込まれる仕組みです。したがって、ドラフトチャンバーでは「コンタミネーションの防止」はできません。
一方で、クリーンベンチの作業エリア内の空気はサッシ開口部からそのまま排出されるため、「有機溶剤や特定化学物質からの作業者の保護」「外気汚染の防止」をすることはできず、お互いを代用することはできません。
ドラフトチャンバーについては、以下の記事で詳しく紹介しています。
ドラフトチャンバーとは?種類・原理・選び方・おすすめメーカーをご紹介
※3… ダクトレスドラフトチャンバーを除く
クリーンベンチの種類
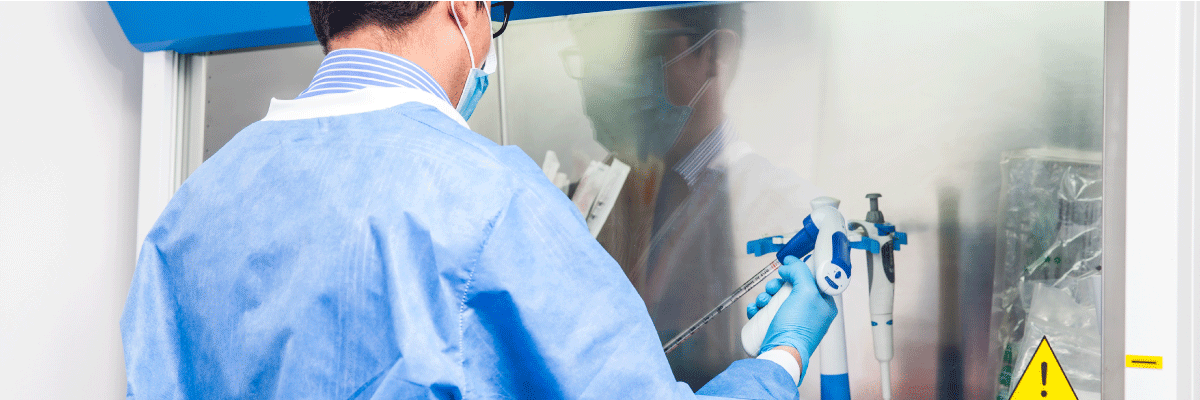
クリーンベンチは、囲われた作業エリアに天井面のHEPAフィルターから清浄な空気が供給され、エリア内の空気はサッシ開口部からそのまま排出されるタイプが一般的です。しかし、さまざまな用途に対応するため、形状や気流の向きなどの異なるタイプがあります。
ここでは従来タイプと合わせて、それぞれの特徴をご紹介します。
形状の違い(据置型と卓上型)
クリーンベンチには「据置型」と「卓上型」があり、それぞれ以下のような特徴があります。
据置型
一般的によく見られるタイプ。床置きで固定が必要なため、一度据え付けると移動が困難な場合が多い。
足部分に移動用のキャスターが付いているものもあるが、装置がダクト接続されている場合や大型機種の場合の移動ルート確保には注意が必要。
卓上型
足部分がない卓上に設置できるタイプ。小型なものが多く、持ち運びができ、比較的狭いスペースにも設置可能。
小型な分、作業スペースは狭くなるが、作業の必要がない時は装置を撤去することで設置場所を通常の実験台として利用できるため、設置スペースが限られている場合に向いている。
気流の向きの違い(垂直層流方式と水平層流方式)
クリーンベンチは、作業エリアへ清浄な空気を供給する際の気流の方向の違いによって「垂直層流方式」と「水平層流方式」に分類されます。
それぞれの方式を比較表にまとめました。
|
 |
 |
| 形状 |
左右・背面の壁と上部の屋根に囲われ、前面にサッシがある |
左右・背面の壁と上部の屋根に囲われているが、前面のサッシがない |
| 作業エリアの気流の向き |
垂直方向:天井から真下(作業台)に向けて |
水平方向:背面から前面(作業者)に向けて |
| 清浄な空気の供給 |
作業エリアの上方から供給されるため、エリア全体で均一になりやすい |
作業エリアの奥側から供給されるため、均一になりにくい |
| 作業者とサンプル等の誤接触 |
前面のサッシにより、物理的な接触が発生しにくい |
発生しやすい |
| 作業台や作業者の手元での滞留 |
滞留しやすい |
滞留しにくい |
| エリア内の装置や作業者の動きによる気流の乱れ |
乱れにくい |
乱れやすい |
| 設置スペース |
天井部分にHEPAフィルターがあるため、高さが出やすい |
背面にHEPAフィルターがあるため、奥行きがでやすい |
| 作業スペース |
前面にサッシがあり、閉鎖的 |
前面にサッシがなく、開放的で操作性が高い |
また、「水平層流方式」には左図のような「屋根と背面の壁がなく、作業エリアを左右から挟み込むのみのオープンタイプ」もあります。
このようなタイプは、左右から対向する気流がぶつかり合い、作業エリアの外側へ向かう気流が発生することで、清浄度の高い空間が形成される仕組みで、上の表とは特徴が異なります。
作業エリアが開放的で操作性が高いことは共通した利点ですが、このタイプは設置が比較的容易で移動しやすく、設置場所の選択肢が多いというのも大きなメリットです。
作業エリアの気圧制御の違い(陽圧型と切り替え型)
基本的にクリーンベンチの作業エリアは「陽圧」に保たれていますが、「陽圧・陰圧」を切り替えられるタイプもあり、「バイオクリーンベンチ」「バイオ用クリーンベンチ」などと呼ばれます。
切り替え型のクリーンベンチには、左図のように「①作業エリアに清浄な空気を供給するためのHEPAフィルター」に加えて、「②室内排気用のHEPAフィルター」が設置されています。陰圧に切り替えると、作業エリアは弱陰圧に保たれ、作業エリア内の空気はサッシ開口部からそのまま排出されることなく、HEPAフィルターを通して清浄化されたのちに排出されます。
ただし、バイオクリーンベンチの目的はあくまで「コンタミネーションの防止」です。完全な封じ込めは不要で、通常のクリーンベンチよりも作業の安全性を高めたい場合に用いられます。したがって、安全キャビネットの代用はできません。バイオハザード対策が必要な病原体や遺伝子組換え生物等などを取り扱う場合は、必ず安全キャビネットを使用してください。
安全キャビネットについては、こちらの記事で詳しく紹介しています。
安全キャビネットとは?種類や機能と選定のポイントをご紹介
判断に迷う場合はメーカーや販売代理店に ご相談 ください。
クリーンベンチの使い方
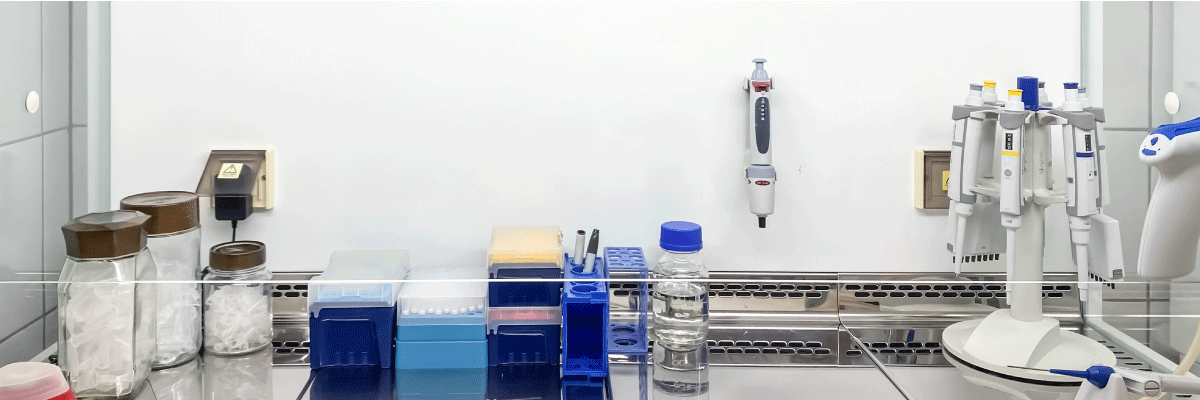
クリーンベンチが本来の性能を最大限に発揮するためには、正しい方法で使用することが不可欠です。
ここでは、作業前に必要な準備や、器具やサンプルの適切な取り扱い方法、使用時の注意点などをご紹介します。
クリーンベンチの使用手順
クリーンベンチの一般的な使用手順は以下の通りです。
- 紫外線殺菌と気流の安定化
- 使用する約1時間前(注1)から紫外線ランプ(殺菌灯)を点灯する(直視厳禁)
- ファンをつけ、前面のサッシを20cm程度(注2)開けた状態でファンが安定するまで5~10分ほど(注3)稼働させる
- 作業者の消毒
- 手や腕を石鹸で洗い、70%エタノールで消毒する
- 手袋や白衣を装着し、70%エタノールで肘の手前まで消毒する
- 作業エリアの消毒
- 道具の準備
- 70%エタノールで消毒した実験器具やサンプル容器などを作業エリア内に入れる
- 高圧蒸気滅菌や乾熱滅菌を行った器具の滅菌袋は開封せず、袋ごと作業エリア内に入れる
- 作業実施
- 作業終了後の片付け
- 70%エタノールで道具や作業エリアを消毒する
- ファンを停止し、紫外線ランプを1時間程度(注4)点灯する
- 廃棄物を処分し、手や腕を石鹸で洗う
注1~4:いずれの数値も目安のため、使用する機種ごとの推奨値を確認してください。
清浄度の高い環境を維持するためのポイント
クリーンベンチを使用する際は、コンタミネーションを防止するため、以下のようなポイントに注意しましょう。
① 気流を妨げない
クリーンベンチは、その気流によって清浄度の高い環境を維持しています。作業を行う際は、気流の乱れを最小限に抑えることが重要です。
- クリーンベンチ前面のサッシは25cm以上開けない
(注意:上記は目安のため、使用する機種ごとにご確認ください。)
- 背後の人の動きや部屋のドアの開け閉めを最小限にする
- 気流を乱さないよう、手や腕はゆっくりと動かす
② 汚染リスクの回避
クリーンベンチの使用前後に消毒を徹底することも、清浄度の高い環境を維持するためには重要です。
気流を妨げないよう気を付けていても、作業エリアや実験器具、作業者自身の消毒が不十分な場合、ほこりや微生物などが侵入してしまう可能性があります。また、作業エリア外への手や物の出し入れや、作業時の動きによってもコンタミネーションのリスクが発生します。
- 作業開始前後は「クリーンベンチの使用手順」で述べた消毒作業を徹底する
- 作業中に作業エリア外に手や物を出した場合は、中に入れる前に都度消毒を行う
- クリーンベンチの使用中は必要外の会話を避ける
- 培地や試薬の入った容器の開封は最小限に留め、蓋を開けたまま作業しない
- 開いた容器の上を手などが通過しないようにする
- クリーンベンチから手を出し入れする際は容器の蓋が閉まっていることを確認する
- 作業エリアの奥側により汚染したくないものを置く
以上を参考に、実際の用途や状況に合わせて、最適な運用を検討してください。
クリーンベンチを選ぶ3つのポイント

ここでは、クリーンベンチを選定する際のポイントをご紹介します。
1.必要な清浄度はどれくらいか
クリーンベンチを選定する際のもっとも重要なポイントは「清浄度」です。使用目的に応じて必要な清浄度は異なります。あらかじめ実施する作業にどれくらいの清浄度が必要なのか確認しましょう。
作業に必要な清浄度のクラスを判断することが難しい場合は、用途を明確にして、クリーンベンチのメーカーや販売代理店に
相談 しましょう。
ここでは清浄度に関わる3つのポイントをご紹介します。
1-1.清浄度のクラス
清浄度は、ISO規格(ISO 14644-1 ※4)においてクラス1~9に分類されています。1m
3の空間内に存在する粒径0.1~5μmの微粒子の上限数(上限濃度:個/m
3)がクラスごとに定められており、もっとも清浄度の高い「クラス1」では0.1μmの微粒子が10個/m
3以下と定義されています。
多くのクリーンベンチは「クラス5」に該当し、カタログ上では「ISOクラス5」「ISO-5」などの表記をされています。また、「クラス100」という表記をされている場合がありますが、これは米国連邦規格(FED-STD-209D)における表記で、ISO規格の「クラス5」に相当します(※5)。(以上、記事公開日時点)
※4 ISO 14644-1… 最新情報については「日本規格協会グループHP」にてご確認ください。記事公開日時点では「ISO 14644-1:2015」が最新です。
※5 ISO規格と米国連邦規格の違い… ISO規格で対象とするのが粒径0.1~5μmの微粒子であるのに対し、米国連邦規格で対象とするのは0.5μm以上の微粒子のため、厳密には定義が異なる。しかしカタログ上では「ISOクラス5(クラス100)」のような表現をされている場合が多い。表記が「クラス100」のみの場合はISO規格についても確認しておくと安心。
1-2.フィルターの種類
クリーンベンチのフィルターは清浄度の高い環境を維持するための要となる部品です。
多くのクリーンベンチはHEPAフィルターを採用していますが、さらに高い捕集効果を有するULPAフィルターを採用する製品もあります。HEPAフィルターは0.3μmの微粒子を99.97%以上除去可能ですが、ULPAフィルターは0.15μmの微粒子を99.9995%除去可能です(※6)。
ULPAフィルターは高価で、目が細かいためにフィルターの交換頻度も高く、ランニングコストはかかりますが、より高いクラスの清浄度が期待できます。
※6 補足… この記事の公開日時点で、HEPAフィルターおよびULPAフィルターは、JIS Z 8122において「定格風量で上記の粒子捕集率を持ち、かつ、初期圧力損失が245Pa以下の性能を持つエアフィルター」と定義されている。ただし、2022年2月21日よりJIS B 9927にて、粒子除去用高性能フィルターの「MPPS(Most Penetrating Particle Size ; 最も透過しやすい粒子径)」の捕集効率に関して定義変更があったため、旧規格のフィルターが新規格の性能を有するとは限らない。詳細については「日本規格協会グループHP」の該当規格を参照。
1-3.層流方式の違い
「垂直層流方式」は天井面から真下(作業台)に向かって垂直方向に清浄な空気が供給され、作業エリア全体に均一に行き届きやすい方式です。また、作業エリアは閉鎖的で、作業者とサンプル等との物理的な接触が発生しにくい形状です。
一方、「水平層流方式」は背面の壁から前面(作業者)に向かって水平方向に清浄な空気が供給され、作業台や作業者の手元に空気が滞留しにくい方式です。また、前面にサッシがなく、開放的で操作性が高い形状です。
それぞれのメリットがあり、どちらが良い悪いということではないため、作業内容に合う方式を選択しましょう。詳しくは「
気流の向きの違い」の比較表を参考にしてください。
2.設置環境や設置スペースを考慮
クリーンベンチを選ぶ際は、本体サイズや設置場所、その周辺環境を確認しておくことも重要です。
クリーンベンチは大きな機器のため、搬入や設置も大変です。本体サイズを確認し、搬入経路や設置場所のスペースが十分かどうか、あらかじめ確認しておきましょう。また、クリーンベンチは気流を制御することで清浄性を維持しているため、出入り口や窓付近などの風が吹き込みやすい場所は避け、周囲に十分なスペースを設けることも大切です。
「据置型」の場合は設置後の移動が難しいため、装置周辺の動線や周辺設備、電源の位置なども確認し、作業の効率を損なわない配置を検討しておくとよいでしょう。さらに「垂直層流方式」の場合は、「気流の向きの違い」で述べたように、比較的高さが出やすい構造になっています。フィルター交換時に十分なスペースが確保できるよう、床面積だけでなく天井の高さにも注意しましょう。
設置スペースが限られている場合には「卓上型」のクリーンベンチがおすすめです。据置型と比べて本体サイズが小さく、比較的狭いスペースに設置可能です。既存の実験台に設置可能で、持ち運び可能なモデルも多いため、設置場所の自由度が高いこともメリットです。ただし、必然的に作業エリアが狭くなるため、必要な作業エリアが確保できるかどうか、あらかじめ確認しましょう。
3. 付加機能は必要か
クリーンベンチには、作業者の使いやすさを向上するため、さまざまな工夫が施されています。必要に応じて、下記のような機能を搭載した機種の導入も検討しましょう。
- エアーカーテン機構による気流制御
作業エリアをエアーカーテン機構で分画し、適切な気流制御を行うことでサンプルの相互汚染を防止する仕組み。
これにより、異なる作業を同時に進行させることも可能となり、作業が効率化される。
- アームレスト
手首や肘にかかる負荷を効果的に分散し、作業中の疲労感を大幅に軽減できる。
長時間にわたる実験や繊細な操作が必要な作業でも、実験の精度を落としにくくなる。
- 警報保安機能
送風機からの吹き出し風速が基準値以下になると、警告灯の消灯やアラーム音で知らせる機能。
視覚的および聴覚的な警告により、作業者が見落としてしまいがちな装置の異常を認識でき、清浄空間の維持に役立つ。
- 紫外線ランプ(殺菌灯)のオフタイマー機能
タイマーで自動的にランプが消灯することで、作業者の手間を減らす。
UV照射時間を正確に管理して、照射によるプラスチック部分の劣化を防ぐ。
上記以外にも、ガスバーナーや給水コック、排気ダクト、バキューム配管、差圧計など、用途に応じて必要な機能を選択しましょう。(注意:いずれもオプションの可能性があります。)
また、完全な封じ込めは不要で、通常のクリーンベンチよりも作業の安全性を高めたい場合は、作業エリアの陽圧・陰圧を切り替え可能な「バイオクリーンベンチ」を検討しましょう。(詳しくは「
作業エリアの気圧制御の違い」を参照)
クリーンベンチを選ぶ際には、清浄度や設置場所、付加機能など、多くの要素を考慮する必要があり、どの機種が最適なのか迷うことも少なくありません。
池田理化では、長年の実績に基づく専門的な知識で、使用目的や作業環境に最適なクリーンベンチを選定するお手伝いをしています。また、現場の条件を踏まえた設置サポートも行っております。
「クリーンベンチの選定に悩んでいる」「現場に最適な機種を知りたい」という方は、ぜひ池田理化にご相談ください。